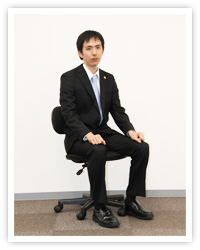1 相続財産清算人は相続人がいないケースで選任される
相続放棄した方から、相続財産清算人の選任申立ての相談を受けることがあります。
以前は、相続財産管理人といわれていましたが、令和5年4月1日の民法改正以降は、相続財産清算人といいます(令和5年4月以降も相続財産管理人という制度はあるのです
が、権限が縮小されて使うケースは少なくなっています)。
相続財産清算人は、相続人がいないケースで、相続財産を利用したい人や相続の対象となるはずの負債を払ってほしい人が裁判所に申請することで選任されます。
ほとんどのケースで、亡くなった方の住所地を管轄する地域の弁護士が選ばれます。
2 相続放棄した人が管理責任を免れたいとき
亡くなった方の子どもや兄弟など相続人となる可能性がある人全員が相続放棄をしても、たとえば相続財産である不動産に居住したり物を保管している場合
は、管理責任がありますので、不動産が崩れて通行人がケガをした場合等に損害賠償請求を受ける可能性があります。
これを免れるためには、全員の相続放棄が終わった後に相続財産清算人の選任申立てをします。相続財産清算人から自宅だけ買えば、相続財産である自宅に住み続けることがで
きるわけです。
3 債権者が相続財産から支払いを求めたいとき
亡くなった方が税金を滞納しており、不動産や保険など財産がある場合、税務当局は不動産や保険をお金にかえて税金を取り立てる必要があります。
このとき、税務当局が相続財産清算人の選任申立てをします。
4 特別縁故者が財産分与を得たいとき
亡くなった方の介護を長年したが血がつながっていない場合に、特別縁故者として相続財産から支払いを受けられるケースがあります。
特別縁故者となる予定の方が相続財産清算人の選任申立てをします。
5 費用やスケジュールなど
相続財産清算人の選任申立ては、一般の方なら弁護士を依頼するケースが多いでしょう。弁護士の費用のほか、裁判所に支払う予納金が相続財産清算人の報酬を確保するために
必要で、現金化しやすい預貯金等が多ければ0円のケースもありますが、一般には70万円~100万円など相当額が必要です。
ただし、相続財産が現金化できたときには返ってくるケースもあります。
相続財産が全てお金にかわって債権者の皆さんに平等に配られるまで続くので、不動産が複数ある方などは1年以上かかるケースもあります。