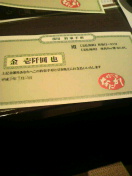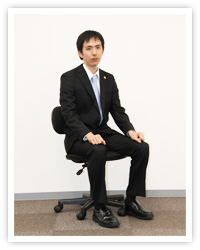住宅ローンの支払いが遅れて,自宅を競売されてしまった場合でも個人再生手続きで自宅を残すことができる場合があります。 競売手続きが始まった場合,個人再生手続開始の申立てを裁判所に行うまで,競売手続きを止めることは原則として不可能です。 競売手続きを止めるためには,競売の申立てをした債権者の意見を聴く必要があるうえ,競売手続きの開札期日を過ぎると,最も高い値段で入札した者の同意がないかぎり,競売手続きを取り消すことができなくなるため,遅くとも,開札期日までには,個人再生手続開始の申立てを行うべきです。 自宅を競売されてしまった方は,お早めに弁護士にご相談ください。
出張無料法律相談会
イオンモール木曽川での出張無料法律相談会に参加してきました。
このイオンは,非常に活況で,子どもたちを含め非常に多くの方がこちらを珍しそうな目で見つめていました。
交通事故や債務整理など,多くの方が相談に来てくださり,ありがとうございました。
採用面接
今日は,事務所の採用面接に立ち会いました。
11月から司法修習生(弁護士,検事,裁判官になるための研修を受ける者)になる方と,2時間ほどお話ししました。
私も,修習生のとき,複数の法律事務所の採用面接を受けましたが,弁護士法人心ほど様々な試験を行い,時間をかけて選考を行っているところは記憶にありません。
弁護士としての基本的な仕事のスタンスは,最初に所属する事務所で決まるといっても過言ではありません。
司法修習生の皆さんが,弁護士としての第一歩を歩むにふさわしい事務所とご縁があることを願っています。
個人再生手続での財産の評価
個人再生を行う際,債権者に返済する金額は,財産の総額より多くなければなりません。
そこで,財産をいくらと評価するかが問題となります。
現金は,手持現金額そのものになりますが,大家さんに敷金を差し入れている場合,敷金を返してもらう権利があるので,その権利をいくらと評価するかが問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として10万円を差し入れていいれば,10万円と評価することにし,引越費用や返還されないことが明らかな部分を差し引くことができるかを,個別に判断するものとされています。
また,友人に100万円お金を貸している場合,お金を返してもらう権利をいくらと評価するかも問題となります。
名古屋の裁判所では,原則として100万円と評価するが,友人と音信が不通であるとか,裁判をして回収しようとしたが差し押さえる財産がなかったことを示す等すれば,0円と評価されることもあります。
このように,財産の評価の仕方により,債権者に返還する金額が大きく変わることもありますので,個人再生の手続きに詳しい弁護士に依頼することが必要です。
個人再生で債権者に返済する金額については,こちらをご覧ください。
信用情報登録
ソフトバンクモバイルが,誤って事故情報を信用登録機関に通知していたという記事を読みました。
弁護士が介入して借金の整理をする際,デメリットになるのが,信用情報機関に事故情報が登録されることです。
事故情報が登録されると,新たにカードが作れなくなったり,ローンが組めなかったりするのです。
ソフトバンクが,携帯電話料金の未払いがないのに,未払いがあるかのように通知していたとすれば,大きな問題になります。
信用情報機関には,CIC,JICC,全国銀行業協会の3つがあり,それぞれ加盟している金融機関が異なり,前の2つがサラ金やカード会社,銀行協会は銀行系が主に加入しているといわれています。
信用情報機関ごとに事故情報を登録している期間も異なり,おおむね5年~10年程度です。
信用情報の詳細については,こちらをご覧いただき,債務整理に詳しい弁護士にお問い合わせください。
新司法試験合格発表
今日、新司法試験の合格発表がありました。合格した皆さま、本当におめでとうございます!
弁護士になるためには越えなければならない関門です。
私は、インターネットで合格を確認したあと、同期で弁護士になった友人と、大阪地方検察庁に合格発表の掲示を見に行き、祝杯をあげました。
今までで一二を争うくらい酒が旨かったのを覚えています。
非嫡出子の相続分の差別
9月4日,最高裁判所で,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が憲法違反であるとの決定が出ました。
この事件では,相続が発生したのが平成13年7月であり,少なくとも平成13年7月以降は,この民法の規定が無効であったというのです。
しかし,平成13年7月以降,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とすることを前提に,たくさんの遺産分割がなされてきました。
これらの遺産分割を無効とすると,遺産分割が成立したことを前提に家に住んだり財産を売却したのが無効になってしまいかねません。
そこで,最高裁判所は,あえて,今回の決定にかかわらず,遺産分割協議の成立等で既に確定した法律関係に影響を及ぼすものではないという趣旨のことを述べています。
裏を返せば,平成13年7月以降に相続が発生したが,未だ遺産分割協議等が成立していない場合には,非嫡出子の相続分を嫡出子と同じとすることを前提に,遺産分割審判等がなされるものと思われます。
相続分について気になる方は,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
決定から3日後,大福もちを食べながら,この記事を書いています。